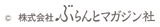かかりつけ医が伝える、あの病気、この症状
糖尿病網膜症

- 江別こばやし眼科
院長
小林 和夫氏 - 2002年札幌医科大学医学部卒業。同大学眼科入局。2009年江別市立病院眼科主任部長を経て、15年5月1日開院。日本眼科学会専門医ほか
糖尿病の3大合併症の一つ。進行すると失明に至る場合も。
適正な血糖値のコントロールと、定期的な眼科での検査が大切
初期には自覚症状がないが、見えるから大丈夫という自己判断は危険
糖尿病網膜症は、糖尿病腎症・糖尿病神経障害とともに糖尿病の3大合併症の一つであり、血糖値が高い状態が長く続くことで、目の奥にある網膜の血管が傷つき、視力に障害を来す病気です。目の一番奥、眼底には網膜という神経の膜があり、多くの毛細血管があります。糖尿病の患者さんの血液は、糖が多く固まりやすい状態になっているため、網膜の毛細血管を詰まらせたり、血管の壁に負担をかけて、眼底出血をしたりします。そのため血液の流れが悪くなり、網膜に酸素や栄養素が不足し、これが糖尿病網膜症の原因となります。進行した場合には、硝子体で大出血が起こり、失明に至る場合もあります。
また、糖尿病が改善せず血糖をコントロールできない状態が続くと、物を見るために重要な黄斑という部分にむくみ(浮腫)が生じて物がゆがんで見えたり、視力が低下を来すことがあります。糖尿病黄斑浮腫は糖尿病網膜症の初期から発症する可能性があります。
糖尿病網膜症は、糖尿病になって数年から10年以上経過して発症するといわれていますが、初期の段階では自覚症状がほとんどないことが多く、進行するまで気付かないケースも少なくありません。まだ見えるから大丈夫という自己判断は危険で、重度になると出血や網膜剥離により突然の視力喪失が生じることもあります。症状が出てからでは治療が難しくなるため、自覚症状が現れる前に診断・治療を行うことが重要です。
また、糖尿病黄斑浮腫は早期でも発症することがあり、「眼がかすむ」「ゆがんで見える」「コントラストの感度が低下する」などがあります。
適切な時期に適切な治療を受けられるためにも定期的な検査が必要
糖尿病網膜症の診断には、問診、視力低下、眼底検査、光干渉断層計(OCT)などの検査が必要です。
問診では、病気の診断や管理、これまでにかかった病気や生活習慣などをお聞きします。眼底検査では、瞳孔を開く目薬を点眼してから網膜の状態を直接観察し、網膜に異常がないかどうか観察します。点眼薬は約4~5時間効いているため、車の運転を予定している場合や、書類を見る仕事があるような場合を避けて検査すると良いでしょう。定期的に眼底写真を撮っているからとの理由で眼底検査を希望されないケースもありますが、糖尿病網膜症では眼底写真では写りにくい周辺部網膜から発症することが多く、早期発見のためには眼底検査が重要になります。光干渉断層計(OCT)では網膜の断面を撮影して、黄斑の状態を確認することができます。黄斑浮腫の診断にとても有用な検査になります。
糖尿病網膜症の治療法は、病状の進行度によって異なり、主にレーザー治療、硝子体手術、抗VEGF薬注射があります。
レーザー治療は、新生血管の発生を予防する治療法です。この治療で視力化回復するわけではありませんが、網膜症の進行を阻止することが期待できます。
硝子体手術は、糖尿病が進行して硝子体出血や網膜剥離を発症した場合に必要になります。
抗VEGF薬注射は、主に糖尿病黄斑浮腫に至った場合の治療法です。むくみにはVEGFという物質が悪影響を及ぼしているため、VEGFの働きを抑えることで、むくみを改善します。
最後に、糖尿病網膜症をくい止めるためには、血糖値をしっかりコントロールすることが重要です。糖尿病と診断されたらできるだけ早く血糖値の目標を定め、治療を開始しましょう。また、日常生活に運動を取り入れ、バランスの良い食事を規則正しく取り、禁煙を心掛けることも大切です。その上で定期的に眼科の検査を受けることで、適切な時期に適切な治療を受けることができます。