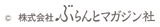かかりつけ医が伝える、あの病気、この症状
肝硬変

- 札幌センチュリー病院
副院長・内視鏡センター長
後藤 哲氏 - 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器病学会専門医。日本消化器内視鏡学会専門医。日本肝臓学会肝臓専門医
自覚症状による早期発見が難しい肝硬変。
リスクとなる疾患の治療や生活習慣の改善はもちろん、定期的な血液検査と腹部エコー検査で早期対策を
肝臓がんの大きなリスク疾患
命に関わる合併症を起こす場合も
肝硬変とは、肝臓が硬くなってしまい、本来果たすべき役割を果たせなくなる病気で、程度によって「代償期」と「非代償期」に分かれます。代償期の肝臓はまだ頑張って機能を果たせていますが、この時期は特に症状が現れないことが多いため、気付かないまま無理が続くと、いずれは完全に機能が果たせなくなる非代償期に進行してしまいます。非代償期になると、例えば、胆汁を十分に作れなくなることで黄疸(おうだん)や貧血が見られたり、体中のむくみ、おなかが腫れる(腹水)といった症状が現れるようになります。このほかにも、食べた物をタンパク質などの栄養素に変えて蓄えることができなくなり、きちんと食べていても痩せてしまうという現象も起こります。さらに、肝臓は解毒作用を持っているのですが、摂取したものが肝臓を通って処理されないまま別の経路を通って全身に流れるようになると、本来であれば無毒化されて尿とともに体外に排泄されるはずのアンモニアが血液中に増えてしまい、それが悪さをして意識レベルが低くなる肝性脳症という合併症を起こすこともあります。また、肝臓の血管も硬くなるため、肝臓に流れるはずの血液が肝臓周辺にある別の血管に流れるようになることで血管が腫れて静脈瘤ができやすくなり、それが破裂し出血を起こすと命に関わる場合もあるのです。そして何よりも、肝臓の構造が根本的に変わってしまうことで腫瘍ができやすくなり、肝臓がんの大きなリスクとなるのです。
脂肪性肝疾患とアルコールの多飲など、生活習慣の改善が重要
肝硬変の原因について、以前はB型肝炎やC型肝炎が最も多かったのですが、今では優秀な治療薬が開発されたことで、C型肝炎は内服薬を一定期間使用することでほぼ完治したと言えるまでの治療成績を収めています。B型肝炎は完治することが難しく、内服薬を飲み続ける必要がありますが、若い方の場合にはインターフェロンという注射薬によって免疫力を高めてB型肝炎ウイルスを体外に排除する方法や、抗ウイルス薬でB型肝炎ウイルスの活動を抑える方法があり、B型肝炎やC型肝炎による肝硬変は減少傾向にあります。
その一方、肝硬変の原因として頻度が高くなっているのが脂肪性肝疾患(脂肪肝や脂肪肝炎)と、アルコールの多飲によるものです。脂肪肝は、基本的に生活習慣病の延長にあり、薬による治療法もありますが、やはり食事や運動などの生活習慣の改善が最優先となります。ただし、炎症をともう脂肪肝炎を起こしていれば、既に肝臓の構造が崩れ始めているため、その状態から生活習慣の改善や禁酒をしたとしても、ある程度の回復は期待できるかもしれませんが、既に硬くなってしまった肝臓は元に戻すことはできません。
その意味でも、一番重要なことは「肝硬変にさせない」ということです。原因疾患の治療はもちろん、生活習慣に問題はないのか。既に脂肪肝になっていないか。アルコールによる肝障害は起きていないか。肝硬変は初期の段階に自覚症状で気付くことはかなり難しいため、少しでも早い段階で肝臓の異常を見つけるためには、定期的な血液検査と、特に脂肪肝の発見には腹部エコー検査が有用となります。また、これまで肝臓の硬さを調べるには肝生検で確定させなければなりませんでしたが、最近では腹部エコーを使ったエラストグラフィという検査方法で肝臓の硬さを推定できるようになりました。特に60歳代以上の高齢な方や体格のいい方は、肝臓の線維化や肝臓がんのリスクも上がるといわれているほか、アルコールによる肝障害は一般的に男性よりも女性で飲酒習慣のある方で起こりやすいといわれていますので、気になる方は、ぜひ定期的な血液検査と腹部エコー検査を積極的に受けていただきたいと思います。