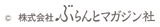診療室からのメッセージ
過敏性腸症候群(Irritable bowel syndrome : IBS)

- 新星おなかのクリニック
院長
中島 淳太氏 - 1995年北海道大学医学部卒業。2008年同大大学院医学研究科卒業。道内主要病院勤務を経て、18年開院。日本消化器病学会、日本消化器内視鏡学会、日本肝臓学会各専門医ほか。医学博士
明らかな腸の病気がないにもかかわらず、腹痛をともなった便秘や下痢などの便通異常を繰り返す病気。治療は心理的負担の軽減が必要な場合も
経験的な感覚では、整腸剤だけでも
症状が改善されることも多い
過敏性腸症候群(IBS)は明らかな腸の病気がないにもかかわらず、腹痛をともなった便秘や下痢などの便通異常を繰り返す疾患です。病気の成因については明らかになっていないことも多いですが、遺伝的要因や環境要因を背景にして心理的社会的要因と腸管運動や微小炎症、知覚過敏、細菌叢(そう)などの腸内環境を含む生理機能的要因がIBSを引き起こすと考えられています。消化管と精神的要素の関係性について最近は腸脳相関という相互作用があることが研究されてきています。
IBSの診断は、RomeIV基準と呼ばれる国際基準をもとに診断されます。RomeIV基準では「腹痛の頻度と排便にともなう症状として排便回数や形状、症状が出ている期間」を元にIBSと診断され、病型には便形状にあわせて下痢型、便秘型、混合型、分類不能型の4型があります(詳しくはクリニックHP参照)。IBSの診断に際して重要なことは、その他の鑑別疾患を除外することで、鑑別疾患として挙げられるものにはクローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患や大腸がん等の悪性腫瘍による便通異常など重大なもののほか、甲状腺機能異常症などの内分泌異常による便通異常、プロトンポンプ阻害薬などによる薬剤性の下痢、アルコール多飲、慢性すい炎、好酸球性胃腸症、食物アレルギーや乳糖不耐症など食物関連による便通異常、胆汁性下痢症などが挙げられます。これらの疾患を除外するためにはこれまでの病歴や服薬歴、生活習慣などを問診で詳しくお聞きしたり、マイナ保険証による診療情報、薬剤情報の取得が非常に役に立つこともあります。実際の診療においては、発症から6カ月以上経過していなかったり、腹痛をともなわないなどRomeIV基準を必ずしも満たさない場合もIBSとして診療することも多くあります。また、仕事や学業などで時間がとれず検査を行わずに治療を先行する場合など、IBSの診断は治療を行いながら、他の疾患の可能性を除外して最終的にたどり着くようなイメージです。
治療法には、薬物療法として便形状をコントロールする高分子ポリマー製剤や消化管運動を調整するセロトニン拮抗薬や便秘型IBSには腹痛を軽減しながら便形状を柔らかくするペプチド製剤など症状に合わせて組み合わせていきます。IBSに有効とされる薬剤も多くないため、腸内環境を整える整腸剤の併用や、薬物療法だけではなく心因性要因の関与が強い場合は生活環境の改善など心理的負担の軽減を図るほか、必要に応じて心療内科、精神科へ併診をお願いすることもあります。IBSの治療の一つに食物に関連した便通異常に対してFODMAP食(発酵食、オリゴ糖、二糖類、単糖類およびポリオール)の制限も挙げられますが、あまり制限食にこだわると食べるものがなくなってしまうことや、こだわりの強さは心因性要素となりかえって病態の悪化につながると考えられるため、当院では積極的に採用していません。
あくまで当院での経験的な感覚ですが整腸剤による腸内細菌叢の改善だけでも症状が軽快される患者さんも多いと思います。腸内細菌叢の評価は残念ながら一般的なクリニックではできないことがほとんどのため、整腸剤による腸内環境の改善は臨床症状の改善をみて評価するしかありません。IBSの治療効果判定を含む症状としての便の形状は口頭ではなかなか伝えることが難しく、患者さんには機能性便秘でもよく用いられるブリストル便形状スケールをみながら便頻度や形状についてお尋ねしたり、時には日記のように記録をお願いすることもあります。研究レベルでは、腸内環境が改善したあと、整腸剤を休むことで悪い腸内環境に戻ってしまうことが分かっているため、整腸剤は継続服用することが重要と考えています。