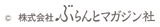かかりつけ医が伝える、あの病気、この症状
難聴
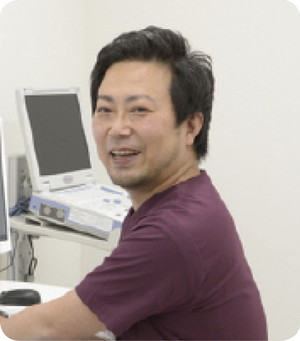
- ほたてクリニックみみ・はな・のど
院長
保立 裕史氏 - 東京工業大学大学院修了。IT関連企業での勤務後、旭川医科大学医学部医学科学士編入学。卒業後、同大耳鼻咽喉科・頭頸部外科入局。道内主要都市の中核病院勤務を経て、2020年5月開院
自覚症状がないことの多い加齢性難聴。認知症にも大きく影響するため、適切なタイミングでの補聴器装用が重要。子どもの難聴は発育にも影響するため日常の挙動に注意を
電子音などの高音が聞こえにくくなったら加齢性難聴の疑いも
聞こえに対して不自由を感じる状態を広い意味で難聴と言います。しかし、難聴は自覚症状のないことが多く、特に、ゆっくりと進行する、年齢にともなう加齢性難聴は気付きにくく、最も多い難聴と言えます。
加齢性難聴の定義は、加齢にともになって内耳が変化することで、聞こえが低下する状態とされています。一般的に50歳代くらいから少しずつ進行し、70歳以上になると症状は顕著になります。聴力が高音から低下してくるのが初期症状としての特徴で、日常生活に支障はなくても、例えば、体温計などの電子音が聞こえにくくなったり、進行すると日常会話の音も聞こえにくくなり、音は聞こえるが会話の内容がよく分からないというように進んでいきます。
特に問題なのは、加齢性難聴が進行すると、認知症に大きな影響を与えることが分かっていることです。年のせいだから仕方がない、それほど生活に支障がないからと放置しておかないでほしいのです。ただし、加齢性難聴は基本的に薬などで治るものではありません。何らかの方法で聞こえを改善するとすれば、補聴器の装用が第一選択となります。しかも、補聴器などを用いることで認知症の進行を遅らせることや、リスク低減が報告されているのです。
その意味では、早い段階から医療介入し、適切なタイミングで補聴器の装用を開始するということが重要となります。会社で健康診断を受けている方は、高音の聞こえにくさを指摘された段階であれば、すぐに補聴器が必要となることは多くありませんが、自覚症状がなくても1年に1回は耳鼻科で聞こえの検査を受けることをお勧めします。健康診断を受けていないという方には、電子音が聞こえにくい、人混みの中での会話が聞こえにくいなどと感じるようであれば一度検査を受けた方が良いでしょう。さらに、一人暮らしの方も注意が必要です。遠方の家族が久しぶりに訪ねた際にテレビの音量が大きいのに気付き、お子さんに連れられて受診される方もいらっしゃいます。特に高齢の方ほど、補聴器を勧めても、さほど不便に感じていない、煩わしいし使わなくていいとおっしゃる方が多いのですが、認知症に対する影響を考えると、ぜひ補聴器を装用してほしいと思います。
子どもでは中耳炎やウイルス感染、大音量のヘッドホン使用も原因に
また、高齢者以外の難聴として、子どもに多いのが滲出性中耳炎による伝音性難聴と、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)などのウイルス感染による難聴です。滲出性中耳炎による伝音性難聴は、適切な治療をすることでほとんどの方は良くなります。ただ、放置されることも多く、将来的に鼓膜の動きに影響が残ってしまうこともあるため注意が必要です。特に小さなお子さんの場合は、聞こえにくさを訴えることが難しく、1~3歳くらいの言語を習得する年齢であれば、言語の習得に遅れが生じる可能性もあるため、耳を気にするしぐさなど、お子さんの挙動に注意を払い、早めに気付いてあげることが大切です。一方、おたふくかぜなどによる難聴は治りにくい場合があるため、そもそもの原因となるおたふくかぜのワクチン接種で予防することも大切と言えるでしょう。
このほか、ヘッドホンなどを長時間装用して大きな音を聞き続けることで生じる騒音性難聴は“ヘッドホン難聴”などとも呼ばれ、若年者で増えています。現代医療では改善することが難しく、発症予防や進行を防ぐためにも、ヘッドホンなどを装用する際は適切な音量と使用時間を守ることをお勧めします。また、どの年代にも起こり得るのが突発性難聴で、治療は早く開始するほど治癒率に大きく影響します。いずれにしても、難聴は早期の治療が重要ですので、耳の聞こえに違和感があれば早めに耳鼻科を受診しましょう。