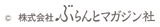がん・脳卒中・心臓病を中心とした急性期医療を提供
全23診療科・チーム医療により専門性の高い診療を展開
「断らない救急」と「体に優しいがん治療」で3大疾病に挑む
がん、脳卒中、心臓病の3大疾病を中心とした急性期医療を提供する札幌禎心会病院。開設当初から専門性の高い医療を実践していることで知られる脳卒中においては、患者の診療および救急受け入れを24時間365日体制で対応。血管障害として共通した病変の多い心臓病に対しても循環器内科と心臓血管外科のスタッフの拡充と緊密な連携により、救急受け入れ体制の充実が図られている。
特に脳卒中の診療においては「断らない救急」を理念に、「1分1秒を争うのが救急医療の現場です。脳卒中は初期対応までの時間で後遺症の度合いや、その後の生活への影響が変わってきます。その難敵を技術と知識、知恵と工夫、熱意と気迫で克服していくのが私たちの役割」(谷川緑野・脳卒中センター長)と、救急対応はもちろん、未破裂動脈瘤や脳腫瘍といった中枢神経系疾患の治療・手術も数多く手掛け、一般的な脳神経外科手術では治療困難とされる巨大脳動脈瘤や頭蓋底腫瘍など、最新の高度な治療を実践している。
心臓病の診療では、狭心症や心筋梗塞、不整脈、心不全、大動脈疾患から末梢血管疾患まで幅広く対応。循環器内科と心臓血管外科が連携し、カテーテル治療と外科手術など、最新の治療を提供。また、地域の医療機関と介護施設の連携を強化し、要介護患者でも急な不調時には、地域包括ケア病棟を活用した即入院治療ができる体制を整え、在宅医療などの支援にも力を入れている。
がん治療では、手術や抗がん剤による化学療法、放射線治療に加え、正常組織への影響が少ない陽子線治療を実施。さらに、「患者の体に優しい治療」を目指し、温熱療法(ハイパーサーミア)や高圧酸素治療といった独自の治療法も併用。各科専門医によるチーム医療で個々の患者に最適な集学的治療を提供。中でも民間医療機関で初めて導入された陽子線治療は、2025年9月末までに計1149例の治療実績を持つ。そのうち保険適用疾患症例は8割以上を占め、既に保険適用とされている小児腫瘍、前立腺がん、一部頭頸部がん、軟骨部腫瘍、肝細胞がん、肝内胆管がん、すい臓がん、大腸がん術後局所再発に加え、24年6月から早期肺がんが保険適用となったことから、今後も陽子線治療に対する需要が膨らむことが期待される。
常に診療機能の拡充と療養環境の充実に取り組み、現在、23診療科を標榜し、診療内容や疾患の部位・症状ごとに特化した外来も開設。「物忘れ外来」、「脊椎・脊髄末梢神経」、「めまい・難聴」、「てんかん」、「がんセカンドオピニオン」、「下肢静脈瘤」、「膝関節」、「血管内留置デバイス」など、より患者のニーズと病態に合わせた診断・治療を提供。一つの病院で患者一人一人を総合的かつ複合的に診られる体制にあるのも同病院の特徴である。
特に脳卒中の診療においては「断らない救急」を理念に、「1分1秒を争うのが救急医療の現場です。脳卒中は初期対応までの時間で後遺症の度合いや、その後の生活への影響が変わってきます。その難敵を技術と知識、知恵と工夫、熱意と気迫で克服していくのが私たちの役割」(谷川緑野・脳卒中センター長)と、救急対応はもちろん、未破裂動脈瘤や脳腫瘍といった中枢神経系疾患の治療・手術も数多く手掛け、一般的な脳神経外科手術では治療困難とされる巨大脳動脈瘤や頭蓋底腫瘍など、最新の高度な治療を実践している。
心臓病の診療では、狭心症や心筋梗塞、不整脈、心不全、大動脈疾患から末梢血管疾患まで幅広く対応。循環器内科と心臓血管外科が連携し、カテーテル治療と外科手術など、最新の治療を提供。また、地域の医療機関と介護施設の連携を強化し、要介護患者でも急な不調時には、地域包括ケア病棟を活用した即入院治療ができる体制を整え、在宅医療などの支援にも力を入れている。
がん治療では、手術や抗がん剤による化学療法、放射線治療に加え、正常組織への影響が少ない陽子線治療を実施。さらに、「患者の体に優しい治療」を目指し、温熱療法(ハイパーサーミア)や高圧酸素治療といった独自の治療法も併用。各科専門医によるチーム医療で個々の患者に最適な集学的治療を提供。中でも民間医療機関で初めて導入された陽子線治療は、2025年9月末までに計1149例の治療実績を持つ。そのうち保険適用疾患症例は8割以上を占め、既に保険適用とされている小児腫瘍、前立腺がん、一部頭頸部がん、軟骨部腫瘍、肝細胞がん、肝内胆管がん、すい臓がん、大腸がん術後局所再発に加え、24年6月から早期肺がんが保険適用となったことから、今後も陽子線治療に対する需要が膨らむことが期待される。
常に診療機能の拡充と療養環境の充実に取り組み、現在、23診療科を標榜し、診療内容や疾患の部位・症状ごとに特化した外来も開設。「物忘れ外来」、「脊椎・脊髄末梢神経」、「めまい・難聴」、「てんかん」、「がんセカンドオピニオン」、「下肢静脈瘤」、「膝関節」、「血管内留置デバイス」など、より患者のニーズと病態に合わせた診断・治療を提供。一つの病院で患者一人一人を総合的かつ複合的に診られる体制にあるのも同病院の特徴である。
傷が残らない婦人科手術が評判
医療・介護の一貫した診療に信頼
24年6月から医師2人体制で診療体制を拡充した「婦人科・vNOTES(ブイノーツ)センター」も注目されている。特筆されるのは、おなかに傷がつかない手術「vNOTES(経腟的内視鏡手術)」を積極的に行っていること。vNOTESとは腹腔鏡手術の一種で、腟を切開しておなかの中の空間に手術器具を入れて内視鏡下に行うため、手術をしても外から見える傷ができず、美容面で優れているほか、通常の腹腔鏡手術やロボット支援下手術より術後の痛みが軽いため、早期の社会復帰も可能となる。しかも保険診療で費用も従来の腹腔鏡手術と変わらないため、身体的にも経済的にも患者負担の少ない術式と言える。
vNOTESの適応は、卵巣腫瘍の手術(卵巣腫瘍のみ切除する卵巣腫瘍摘出術、卵巣・卵管ごと切除する付属器切除術)、子宮筋腫や子宮腺筋症、子宮頸部異形成に対する子宮全摘術など、婦人科の良性疾患のほぼすべてで適応となるが、がんや子宮筋腫核出術の場合は原則適応外(一部限られた症例で適応となる場合も)となる。さらに、vNOTESは従来の腹腔鏡手術より難しいため、実施していない医療機関もあるほか、巨大な子宮筋腫の子宮全摘術や子宮内膜症・チョコレートのう胞などによる癒着などの重症例、妊娠出産経験がない人、帝王切開やその他の手術既往がある人を適応外としている施設もある。しかし、同病院ではvNOTESの経験が豊富な婦人科腫瘍専門医・腹腔鏡技術認定医が手術を担当することで、他の医療機関でvNOTESが難しいと言われた症例にも数多い手術実績を持っている。「お困りの事があれば、お気軽にご相談ください」(西村真唯婦人科医長)。
「超高齢化社会を迎え、3大疾病をはじめ複数の疾患を持つ高齢患者さんも増えていることから、各診療科や各部門が連携し、患者さん個々に最も適した治療法を選択し提供できる診療体制が求められています。私たち禎心会グループは当病院を中心に医療と介護の複合体であるという強みを生かし、今後も定期的な健診や予防への取り組み、最高レベルの質の高い急性期医療をはじめ、その後の在宅医療や介護支援までの一貫した診療を提供し、より地域の皆さんに満足していただけるよう努めてまいります」(徳田理事長・院長)
vNOTESの適応は、卵巣腫瘍の手術(卵巣腫瘍のみ切除する卵巣腫瘍摘出術、卵巣・卵管ごと切除する付属器切除術)、子宮筋腫や子宮腺筋症、子宮頸部異形成に対する子宮全摘術など、婦人科の良性疾患のほぼすべてで適応となるが、がんや子宮筋腫核出術の場合は原則適応外(一部限られた症例で適応となる場合も)となる。さらに、vNOTESは従来の腹腔鏡手術より難しいため、実施していない医療機関もあるほか、巨大な子宮筋腫の子宮全摘術や子宮内膜症・チョコレートのう胞などによる癒着などの重症例、妊娠出産経験がない人、帝王切開やその他の手術既往がある人を適応外としている施設もある。しかし、同病院ではvNOTESの経験が豊富な婦人科腫瘍専門医・腹腔鏡技術認定医が手術を担当することで、他の医療機関でvNOTESが難しいと言われた症例にも数多い手術実績を持っている。「お困りの事があれば、お気軽にご相談ください」(西村真唯婦人科医長)。
「超高齢化社会を迎え、3大疾病をはじめ複数の疾患を持つ高齢患者さんも増えていることから、各診療科や各部門が連携し、患者さん個々に最も適した治療法を選択し提供できる診療体制が求められています。私たち禎心会グループは当病院を中心に医療と介護の複合体であるという強みを生かし、今後も定期的な健診や予防への取り組み、最高レベルの質の高い急性期医療をはじめ、その後の在宅医療や介護支援までの一貫した診療を提供し、より地域の皆さんに満足していただけるよう努めてまいります」(徳田理事長・院長)

- 理事長・院長/徳田 禎久氏
- 1971年札幌医科大学卒業。日本脳神経外科学会専門医、日本脳卒中学会専門医、日本リハビリテーション医学会認定臨床医、認知症サポート医、日本抗加齢医学会専門医